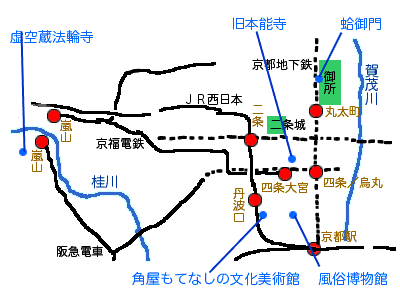
2008.5.11.up ※2017.5.23.切れたリンクを整理
近郊の校外学習(遠足)や修学旅行の班別行動などで、京都をグループで散策する(させる)場合がよくあると思います。
もちろん、有名なスポットだけでも回りきれない京都ではありますが、このページでは、私の知っている範囲での、「あまり知られていな いけどちょっと面白い京都の見学ポイント」を、いくつか紹介してみようと思います。参考にしてください。
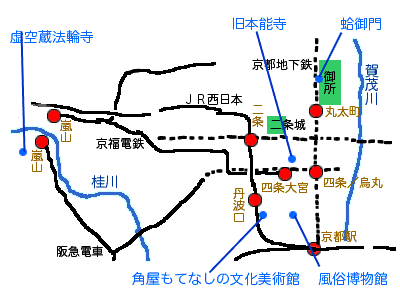
(写真はクリックすると拡大するものもあ ります)
(1)風俗博物館
公式サイト:http://www.iz2.or.jp/top.html
ここは、井筒法衣店という企業の先代の社長さんによって昭和49年に開館された、 個人運営の博物館です。場所は、井筒南店ビルの5階。このため、ぱっと見ただけでは気づきません。
|
ビルの横にこんな掲示あり。 |
 |
開館当初はさまざまな時代の風俗を再現して展示しておられたようですが(名称の由来です)、現在は平安時代、特に『源氏物語』の世界を再現することに猛烈に力をいれておられます。最 大の見所は、源氏の邸宅である六條院の「春の御殿」を4分の1サイズ模型。 建物だけでなく、人形を多数使って『源氏』の場面を再現しています。
さらにさらに、展示室の一角には「実物大」コーナーがあり、当時の調度などが復元されているだけでなく、男性用と女性用の衣装を着ることができます(別料金なし)。
悪ノリして、男女両方を着てみました(^^;
 ↑光源氏さまに寄りそう私 |
||
| ←等身大の女性の人形 | ||
 |
←狩衣(かりぎぬ)姿の私 |
|
残念ながら、生地は絹ではなく化繊とのことですし、十二単も一枚一枚重ねていくのではなくセットされています。そのかわり気軽に着る ことができますし、見た感じは十分です。
男性用はちょっと一人では着れませんし、女子用でも正しく着るためのコツなどもあり、受付の方に声をかけて手伝ってもらいましょう。丁 寧に説明していただけますし、シャッターも押してくれました。入館料は300円と格安。平安時代や『源氏物語』に興味のある人には絶対オススメのスポットです。日祝がお休みなので、今回はチャン スです。
(最寄り:市バス「西本願寺前」すぐ)
(2)蛤御門
時は幕末1864年、前年の八月十八日の政変で京都を追われた長州藩が逆転を期して京都へ進軍し、薩摩・会津ら公武合体派(新選組含 む)と激突。その主たる舞台となった最前線がここ、蛤御門です(禁門の変)。 天皇は「玉」であり、その争奪戦だったわけですが、御所を背にする敵に向けた長州軍の弾丸は結果的?に御所に向けて放たれたことになり、 戦闘に敗れたこともあって長州はいっきに「朝敵」となってしまいました。
その時の銃弾(砲弾じゃないよ)の跡が、ここ蛤御門のあちこちに残って います。まさに歴史の痕跡です。
|
|
 |
| |
↑今も残る弾丸の跡↓
|
 |
 |
|
↓弾痕をアップで撮影
|
|
 |
ここは、まったく観光地ではありません。説明板もありますが、観光客に会うことは滅多にないでしょう。ただ、歴史の回想に浸るには無 理があります。というのは、門の内側は(当然ですが)京都御所。公園としては「京都御苑」で、京都市民にとっては日常の憩いの空間です。 家族連れの楽しそうに遊ぶ姿が目につきました。まあ、それも一興かも。
もちろん見学無料です。幕末好きの方には楽しめるスポットかと。
(最寄り:市バス「烏丸下長者町」すぐ。ただし本数が少な い。または地下鉄「丸太町」「今出川」より徒歩10分)
(3)旧本能寺
「敵は本能寺にあり」
織田信長が京都の定宿に使っていた本能寺。1582年、そこを襲った明智光秀。最近では、その黒幕が誰かをめぐって様々な説が飛び交 い、ミステリーが広がっているようです。そういえば、信長は実は死んでいなかった、なんて小説もあったなぁ。
まあ想像は想像として、信長が、濃姫が、森蘭丸が、華々しく散った本能寺。歴史の大きな転換の場面。ガイドブックには、現在の本能寺 が必ずのっており、そこには信長たちの墓もあるわけですが…。
実は、本能寺はその後(といってもわずか5年後ですが)、秀吉の命令によって移転しています。現在の本能寺は、その移転先であり、信長 が自害した場所ではありません。
で、もとの本能寺のあった場所ですが、残念ながら寺などはもちろんありま せん。現在では、写真のような碑が立っているだけです。その場所に今あるのは、京都市立堀川高等学校本能学舎と京都市本能特別養護ルー ム。本能寺は地名になっています。
「能」はわざとこんな字にしています。地図のCから撮影した写真。 手前の南北の道が油小路、右奥への東西の道が蛸薬師なので、この角が本能寺の西南隅だったことになります。↓ ↓地図のBに残る古い跡碑→
1992年には付近の発掘調査が行われ、堀の跡や本能寺の「能」の寺(ただし異体字)の瓦が見つかっています。 もっとも、当時の 本能寺は広く、ここはその西南隅です。当時の寺域は、北は六角通,南は蛸薬師通,東は西洞院通,西は油小路通という広大なものでし た。想像を働かせて信長の最期を思い描くなら、東北方向を向きましょう。もちろん無料です。
(市バス「堀川蛸薬師」徒歩5分)
(4)「余裕」があればこんなところもあります…
○角屋おもてなしの文化美術館
京都の歓楽街であった島原。その揚屋(現在でいえば高級料亭。遊郭ではない) の一つがこの角屋で、400年前に移転してきた時の建物が残っています(重要文化財)。中には新 選組の隊士がつけた柱の刀傷や、芹沢鴨の最後の宴会となった部屋(ただし再建)などもあり、興味深いものです。
400年を越える建物2階はさらに豪華で、斬新な建築デザインと年月の重みには圧倒されます(2階は写真撮影不可)。
ただネックなのは入館料で、高校生でも800円。2階は別料金+600円で、 こちらは時間制で事前の予約が必要です(案内の方が丁寧に説明してくれますが)。場所もちょっと不便。興味があまりない人にはキツいかも しれません。よく相談してね。
(市バス「島原口」から西へ徒歩10分)○虚空蔵法輪寺
集合・解散場所からすぐ近く。小高い丘の上にあるお寺。「十三まいり」のお寺として知られています。「十三まいり」とは、数え年13 歳になった子どもが、虚空蔵菩薩にお参りして知恵を授かる行事です(「知恵もらい」とも)。うーん、高校生も知恵をもらえたらいいのに。
寺は、奈良時代初期の713年創建で、有名な行基が開基と伝えます。『枕草子』や『平家物語』にも記述があるそうです。ただ、応仁の 乱や幕末の禁門の変の時など兵火にあい、現在の建物は明治以降の再建です。
ちょっと階段を登らなければならないのがネックですが、展望台から嵐山 近辺がよく見渡せますし、知恵をつけてもらうべくお参りしてもいいのでは。特に拝観料はいりません。また余談ですが、人気テレビ番組「ク イズヘキサゴン2」の冬スペシャルでリレークイズ(間違ったら住職に渇を入れられてました)をやっていた場所でもあります。
駅から近いし、知恵を授かりにのぼってみますか?(阪急「嵐山」から徒歩10分)
このほかにも、数少ない平安京の遺構である神泉苑(地下鉄「二条城前」:公式)とか、秀吉の朝鮮出兵で敵兵の首のかわりに持ち帰った耳や鼻を 葬った耳塚(市バス「博物館 三十三間堂前)とか、「国宝第1号」の弥勒菩薩像がある太秦広隆寺(京福電鉄「太秦広隆寺」)とか、ミステリアスな「三柱鳥居」のある木嶋(このしま)神社(京福電鉄「蚕 ノ社」)とか、ライブカメラがあってうまく映れば世界に姿が流れる金閣寺(市バス「金閣寺前」)と か、それこそキリがないのでやめときます。