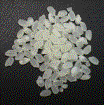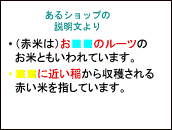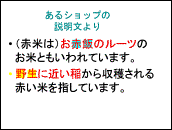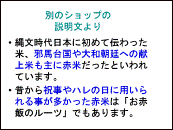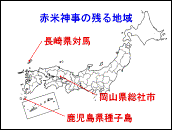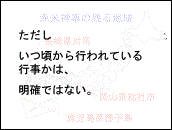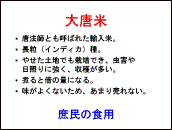このページは、私が現任校(大阪教育大学附属高等学校平野校舎)の『研究紀要』(12号:2008年3月発行)に発表した同名の小考を再編集したものです。その主目的は、カラー写真(研究紀要では白黒印刷になったため)と、誌面では再現できないスライドショーを公開するためです。従って、内容・文章はほとんど同じです。また、印刷の便宜も考え、カラー版のPDFもupしておきます。拙いものですが、ご笑覧ください。
画像はクリックで少し大きな画像が別画面で開きます
要 旨
本稿は、日本史における「主題学習」の試みとして、昨年度に実施した研究授業の報告である。コメという身近な題材を通じて日本史を捉えることで、生徒の歴史への見方をより豊かにすることをねらっている。今回は、古代から近世を対象とし、特に赤米に着目してみた。木簡などに見える古代の赤米と、中世に大量に輸入された赤米(大唐米)とは、品種も扱いもまったく異なるものであり、そこから中世社会の一側面が窺える。また、近年赤米は古代米としてブームになっており、さらに赤飯の起源でもあるという情報が広まっているが、その情報は鵜呑みにできない。こうした点を、資料(史料)を検討しながら考えさせたい。また実物の赤米(モミ)に触れさせるなど、実物教材や視聴覚系教材も活用する。
[I]はじめに
1.主題学習について
高等学校の「日本史」には、一般にはあまり知られていないが、いわゆる"通常の学習"とは別に「主題学習」が教科内容として盛り込まれている。
例えば、日本史Aの現行の学習指導要領には、「身近な生活文化や地域社会の変化などにかかわる主題を設定し追究する学習を通して,歴史への関心を高めるとともに,歴史的な見方や考え方を身に付けさせる」と明記されている。
また日本史Bには、「歴史と資料」として「様々な歴史的資料の特性に着目して,資料に基づいて歴史が叙述されていることを理解させる」ことも求められている。
昨年(2006)6月、校内での研究授業の機会を与えられた。これを、普段なかなか時間が確保できない主題学習を試みる好機と捉え、以前から考えていた題材による授業を計画した。それが「コメと日本史」である。
2.コメという題材について
現行の学習指導要領において、いくつかの「主題」が列挙されている。その中の一つに、「衣食住の変化」(日本史A)がある。
日本史の"通常の学習"では、政治・経済・社会など幅広く学習するが、資料の制約などから、どうしても社会全体の動向や権力側の視点が中心になっている。その点、食という「身近な」ものを通して、違った角度から歴史を学ぶことは、生徒の歴史への見方を豊かにすることにつながることが期待できる。
中でもコメは、弥生時代から現代にいたる歴史の中で、量的にも質的にも、食文化の中心を担ってきた農産物である。また、政治や経済との関係も深く、きわめて日常的で身近であり、生徒の関心も比較的高い。そこで、コメを通して日本史を見直してみる、という学習を計画した。
ただし、コメが関わる歴史事象は広く豊かであり、概観するだけでも1時間ではまとまらない。そこで前後半の2時間に分けて学習する形態を想定して企画し、研究授業ではその前半1時間の授業を行った。
3.資料から考えるということについて
上述の学習指導要領を待つまでもなく、歴史は「資料に基づいて」叙述されているのだが、教科書などで歴史を学んでいるだけでは、そのことを実感しにくい。また、資料の解釈は一定不変ではなく、誤りや誤解を含んでいる場合もある。その意味でも、資料に直接触れること、資料から考えることは重要である。
今回の授業では、赤米を話題の中心とした。本物の赤米に触れさせ、さらに当時の資料(史料)を取り上げて、赤米について考えさせたい。特に、通説になりつつある「赤米は赤飯のルーツ」という説について検討し、そのことを通じて、資料から考えることの重要性と、メディアに流れる情報に対する姿勢について考えさせたい。
[II]実践報告(学習指導案より)
実施日 2006(平成18年)6月14日
対象 2年3組
場所 社会科教室
1.単元名
日本史A (1)歴史と生活 「ア 衣食住の変化」のテーマとして「コメと日本史」を設定
2.単元のねらい
- 近現代史を重点に学習している現在の授業を一度離れ、身近な生活文化の変化にかかわる主題を設定し追究する学習を通して、歴史への関心を高めるとともに、歴史的な見方や考え方を身に付けさせる。
- 日常の生活の中で接している食物がどのように変化してきたかを、社会的な背景と関連付けて追究させる。
- 「日本史A」の範囲は本来近現代であるが、このテーマについては前史としての古代〜近世の内容を欠くことはできない。ただし、できる限り近現代との関連を意識した。
- コメという極めて身近な食材を題材に、それぞれの時代を生きた人々の生活や社会について、通常の歴史学習とは異なる視線で考察させる。
- 稲穂・赤米・タイ米・糒(ほしいい)など具体的な教材をできるだけ用意して、触れ・感じる要素を強める。また、プレゼンテーションソフト・ビデオも併用し、視覚に訴えることで理解を深める。
3.単元の指導計画(2時間を想定)
(1)指導計画の概要
第1時 日本史の中の「赤米」
古代〜近世を中心に、2種類の「赤米」を通して、当時の食生活やその社会背景を考える。
第2時 さまざまなコメと日本史
近現代を中心に、植民地支配とコメ、冷害とタイ米など、さまざまな話題を概観する。
(2)本時の目標
- 赤米は、"古代米"として近年話題になっている。それをふまえつつ、情報リテラシーという観点から批判的な視点を持たせたい。
- 特に、古代の赤米と中世の赤米の違い、赤飯との関係など、具体的に考えさせたい。
- 本校は、都市部に住む生徒が多い。赤米に限らず、コメについて実際に触れ、考える機会を持たせたい。
(3)本時の展開
指導内容 |
指導上の留意点 |
備考 |
|
導入 5分 |
・今日の授業についての説明 |
・日本史Aの単元「歴史と生活」の意義を理解させる。 |
|
展開1 |
・赤い色素(タンニン)があるのは果皮や種皮であることを確認。
・この赤米は丈が高く1m50cmを越え、倒れやすい。 |
<P>はプレゼンテーション画面を示す。 <V>はビデオ映像を示す。 |
|
展開2 |
[1]の典型的な答(赤米=赤飯のルーツ)は通説化してはいるが、疑問の余地がある。 ・「赤飯」は、祝い事など特別の日に食べるものである。では、赤米はそのように食べられていたのかが問題。 ・平城京の造酒司跡から、赤米の木簡が複数出土している。このことから、(赤飯より)むしろ、酒との関係が考えられる。 ・因みに、『魏志倭人伝』には赤米の記述はない。
・ただし、神事の始まった時期が特定できないことに注意。 ・正解は分からない。味、色、価格など忌避された理由を色々と考えさせる。 |
※この質問は口頭のみ <資>は配布した資料を示す |
|
展開3 13分 |
・下等米としての赤米の存在 ・庶民の食用であったこと、新田開発などが解答例。 |
||
まとめ 5分 |
(1)古代の稲作について より野生に近い赤米も栽培されていたが、奈良時代以降はその形跡が残っていない。 (2)赤飯と赤米の関係については、よく分からない。 (3)中世に輸入された第二の赤米である大唐米は、下級米として消費者からは忌避されたが、生産者の生活を支える重要な作物だった。 ※後編では、近代以降のアジアとの関係を中心に、コメと日本史の関係を考えていく。 |
(2)分からないことを尊重すること、ネット上に限らず、情報を鵜呑みにしてはならないことを理解させたい。 |
|
(4)主な参考文献
九州歴史博物館Web「路知」赤米今昔物語 〜赤米に魅せられて〜
[京都文教短期大学教授 安本義正(やすもと・よしまさ)]
http://www.kyuhaku.com/pr/roji/roji_top.html
黒羽清隆『生活史でまなぶ日本の歴史』地歴社 1984年
佐原真『大系日本の歴史』1 小学館 1987年
坪井清文「稲作文化の多元性−赤米の民俗と儀礼」『日本民俗文化大系』1 小学館 昭和61年
旧版教科書『高校日本史B』平成6年検定版 実教出版社
嵐嘉一『日本赤米考』雄山閣出版 1974年
阿部泉「米」『日本史モノ教材−入手と活用』地歴社 1993年
柳田国男「故郷七十年」『定本柳田国男全集』筑摩書房 昭和46年
(5)資料と出典
- 授業プリント
1) 「天平六年尾張国正税帳」は竹内理三編『寧楽遺文』上(東京堂出版 1981)より
2)井原西鶴『好色一代女』巻四「栄耀願男」は『日本古典文学大系』47(岩波書店 昭和32年)より引用
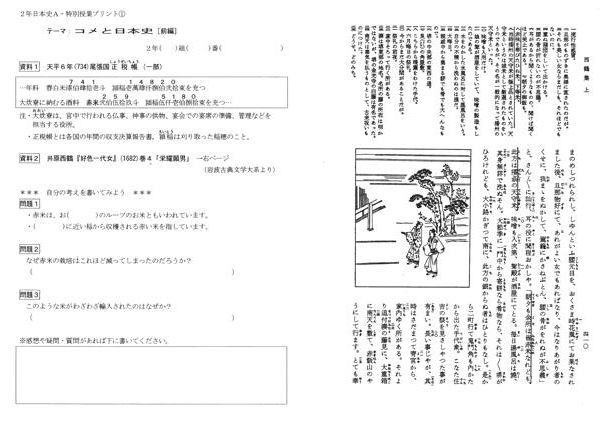
※拡大写真はこちら(243KB) - 木簡
写真・釈文ともに、奈良国立文化財研究所の公式サイト(http://www.nabunken.go.jp/)の木簡データベースのデータを使用した。
なお、授業で使用したのは、平城宮跡から出土した「山田郡建侶酒部枚夫赤米」と記されている荷札(木簡番号2253)。 - 朝鮮通信使黄愼の旅行記『日本往還日記』より(谷川健一編『日本庶民生活史料集成』27 三一書房 1981)。※黄愼は通信正使として慶長元年(1596)に来日している。
※瞿麦(くばく)、蜀■(こうりゃん) ※■はのぎへんに朮但将官の外は皆赤米を用ゐて飯と為す。形は瞿麦の如く、色は蜀■に似る。殆んど下咽に堪へず。蓋し稲米の最悪の者なり。 - 赤米に関する昔話(岡山県児島郡)の要旨(関敬吾編『日本昔話大成』10 角川書店 1987年より)
貧乏人の子供が赤米を食う。家主の家に遊びに行って何を食っていると問われて赤米だと答える。小豆が盗まれるので、主人はその父親を責める。父が子供の腹をさくと赤米が出る。家主は申し訳に自殺する。それから、赤米(大唐米)をつくらなくなる。 - ビデオ
テレビ番組「古代史ドキュメント 遙かなりイネの旅」を一部使用。
4.授業の状況
(1)生徒の反応
おおむね計画通りに授業を進めることができた。普段の授業では消極的な生徒も含めて、高い関心を示してくれた。以下、生徒の感想・質問から抜粋する。
★実物教材・作業・ビデオなど授業形態について
- 疲れた〜。でも楽しかった。
- いつもの歴史と違う感じでおもしろかったです。
- 実物を見れて楽しかったです!
- 赤米の皮をがんばってむいた。
- 面白かったです。VTRが少し短かったけど。 …a
★コメを扱ったことに対して
- 身近な米の話やったから、興味を持ちやすかった。
- 米はよく見るけど、なかなか元のは見ないよね…。
- 身近なお米にもいろんな歴史があったんだなぁと感慨深かった。
- 米って深い・・・。やっぱり、日本人と米とは切っても切れないなぁと思った。
- 米から身分制度の話になるなんてすごいなと思った。
★赤米について
- 赤米の存在をはじめて知った。
- 赤米の他に何か古い米があると聞いたのですが(緑米?)。
- 玄米も赤米も同じ味、栄養なんですか?
- 全体的にすごくおもしろい話ばかりで、赤米っていうのはすごい歴史があるんだなぁと思ったし、米によっていろんな歴史があるんだなぁと思いました。
- 玄米・赤米を食べてみたいと思った。 …b
★その他
- 岡山県の話はとても生々しくて気持ち悪かったが、歴史的にも貴重な話を聞けてよかった。
- 最後の話はすごくかわいそうだった。
- インディカ米といえば、何年か何十年か前の冷害でタイから輸入したが、日本ではまったく口に合わなかったとかいうのがあったそうな。 …c
- 自分の知らないことってたくさんあるんだなぁ・・・と思った。あと、ネットなどの言うことは、まげて伝えられてるってことも
☆補足
aについて…
生徒に見せたのは、「赤米の収穫風景の映像」「種子島宝満神社の神事の映像」の2回をあわせても1分に満たない。
これは、全体として時間がなかったという面もあるが、番組の中で語られている解釈(「赤米は日本のコメのルーツである」云々)の部分を避け、客観的な事実の映像のみ提示したかったからである。
bについて…
今回は赤米の試食は実施していない。その事情について述べる。
実はこの赤米を使った授業は、前任校(大阪府立城山高等学校:平成20年3月をもって閉校される)において、1996年に高校生ではなく一般に向けて開講した「学校開放講座」の内容をベースにしている。この講座では参加費を徴収することができたので、それを使って赤米を大量に購入し、調理実習室をお借りして、炊きたての赤米を試食することができた(お土産としても持ち帰っても
らった)。
今回の授業で使用した赤米は、その時に購入したものの残りである。よって10年が経過しており、試食させたいのはやまやま乍ら、安全面から生徒に食べさせるのは断念した。
因みに、味は通常の玄米とほぼ同じである。
cについて…
この生徒が指摘する通り、1993年の天候不順による深刻なコメ不足(作況指数74)の際、タイをはじめとする東南アジア各国からインディカ米を大量に輸入し、これが日本人の好みに合わなかったことからさまざまな社会問題が起こっている。
この点については、「3.単元の指導計画(1)指導計画の概要」に述べた通り、第2時「さまざまなコメと日本史」で触れることを想定していた。実は上述の1993年に、教材用としてタイ米を購入して一部保存しており、比較させる予定だったが、時間の関係などで残念ながら実現できなかった。
5.おわりに
「赤飯の起源は赤米」説であるが、どうも柳田国男が震源らしい(各サイトにもよく名前が使われている)。調べてみたところ、「故郷七十年」(昭和33年に『神戸新聞』に連載)に「赤米のこと」という節があり、その中で、「これは私の奇抜な解釈だが」と断った上で、「在来の赤米がだんだん少なくなって來たので、それによく似た小豆御?を炊くことになつたのではないかと私は考へてゐ
る」などと述べている。
もっとも、当の柳田が「奇抜な解釈」と非常に慎重な言い方をしていることには、もっと注目すべきだと思う。柳田の言葉もまた、歴史の資料である。
授業としても研究としても、未完成で不十分なものであることは否めない。反省しつつ研鑽を重ねていきたい。
最後に、授業で使ったスライドショー(PowerPoint)の一部(公開にあたって支障のある箇所は削除しました)とカラー版PDFをupしておきます。リンクをクリックしてダウンロードしてください。